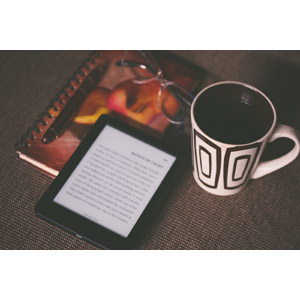ー彼の日常一
彼は彼女と暮らしていた
付き合いは、もう3年ほどになる
彼女は何も言わない
いつもおとなしく、彼の帰りが遅くなっても黙って彼の帰りを待っている
彼の帰りが遅いのは、仕事が終わるとほぼ毎日パチンコ店に寄っているからだ
元々彼はパチンコがかなり好きな方だ
付き合い始めの頃は、彼女を優先してパチンコは控えていたが、半年、1年とたつごとにパチンコに行く日も増えていった
休みの日も、丸一日一緒にいる事は珍しい
それでも彼女は何も言わなかった
ただいつもおとなしく、彼の帰りを待っていた
どんなに遅くなっても、彼が一緒にご飯を食べてくれるのが嬉しそうだった
そんな彼女との生活に、彼は慣れてしまっていた
一彼女の日常一
彼女は朝9時から午後6時まで週5日パ一トに出ている
タ飯の仕度も午後8時には済ませてしまうと、午後23時過ぎまで、ほぼ毎日一人で彼を待っている
そして彼が帰ってくると、とても嬉しそうに遅いタ飯の用意を始めるのだった
そういった彼女の半ば献身的な態度には理由があった
一彼女の事情一
彼女には幼ない頃から母親しかいなかった
彼女が1さいになる頃には、両親は離婚していた
理由は分からない
母親は一人で彼女を育てる為に昼夜懸命に働いた
それだけならまだ良かった
不辛な事に彼女が5歳になった頃、心蔵の病気を患った
治療には大きな手術が必要だった
母親は親戚や友人に頭を下げ、消費者金融からも借金をして、なんとか手術代を工面した
一一一手術は成功
しかし母親は大きな借金と抱える事となった
生きていくために、母親は水商売の世界に身を投じた
今までよりはるかに収入が良くなったが、母親の身なりも彼女への態度も変わっていった
彼女は幼いながらも、それが自分のせいだと理解していて、何も言わずいつもおとなしくしていた
彼女が高校に上がると
ーと言っても定時制だが
母親はひんばんに男を家に招き入れるようになった
彼女は昼間バイトをしていたが、夜学校から家に帰る度母親が男に寄り添う姿を見ることとなった
時には行為の最中を目にする事も
しかも、ほとんどが違う男だった
彼女はそれさえも自分のせいと戒め、部屋ではそれの声や物音が聞こえないように、そして自分がいる事までも気付かれないようにおとなしく過ごしていた
そんな日々もやはり次第に苦痛になり、深夜まで外で男が出ていくのを待つ亊が多くなった
ある日、いつものように外へ出ようとした時、玄間でバッタリ知らない男と鉢合わせた
男は母親の呼んだ客だった
母親は不在
約束の時問より早く着いてしまったと悪びれながらも、彼女の身体を観察するかのような視線
彼女が男に軽い会釈を送り、横をすり抜けようとすると、男は彼女の腕をつかんで引き寄せた
顔が近くにくる
息が荒い
気持ち悪い
早く逃げたい
ー刹那
母親の声がした
男はうすら笑いを浮かべつつも、彼女から手を離した
彼女は走りだした
と言うより逃げ出した
母親は何か言っていたようだったが、構わなかった
とにかく「そこにいるのが嫌だった」
行くあてなどなかったが、何となく駅に向かっていた
駅ならどこか遠くに行けると思ったのかもしれない
だが今は財布すら特っていなかった
もうすっかり日が暮れていた
家に帰る気にはなれなかった
彼女は夜通し駅の近くを歩いて過ごした
どこかで休んで寝てしまったら、知らない男に襲われるかもしれないと考えたからだった
何時間も歩いては休み、人の気配がすると何事もなかったようにまた歩き一一一
まわりが少しずつ明るくなり始めた
さすがに疲れと空腹がおしよせてきたので、とりあえずどこかで座って休む事にした
駅前にあるベンチに向かうところで足がもつれて派手にコケた
ヒザと手のヒラから血がにじんだが、とりあえずべンチで座ろうと立ち上がった
その勢いが良すぎたのか、前を良く見ていなかったせいもあって、今度は人とぶつかってまたコケた
何もかもが上手くいかない
すべて自分のせいなのだろうか
これからも・・・・
涙が溢れる
ー始まりの朝ー
ぶつかった男性が反射的に彼女に声をかけた
何を言っていたかは分からない
男性とは目を合わせないまま
それでも何度も何度も頭を下げた
ぶつかって申し訳ないと思ったが、今は構わないで欲しかった
彼女は手を左右に振り、大丈夫の意を示した
涙を浮かべながら手とヒザに血が滲み
何だか落ち着かない、そして不安げなその様子
どう見てもいろいろと大丈夫そうではなかった
男性がその姿に疑問を投げかけようとしたその時に、彼女のお腹が
グウと鳴った
一瞬の時が過ぎて
彼は声を殺して笑った
彼女は恥ずかしさのあまり、耳までまっ赤になった
彼はちょっと強引に彼女の手を引いて歩き出した
抵抗の意思を表したが、今の彼女にはそんなカも判断力もなかった
言い訳をするなら、彼の笑顔はどことなく安心できる優しさがあった
きっと誰かに助けて欲しい気持ちもあったのだろう
5分ほどで着いたところは駅前によくあるコーヒショップだった
彼女を空いてる席に座らせ、カウンターに注文に向う
戻てきた時には2人分のホットコーヒーとソーセージドッグ
その一つを彼女の前へ
そして数枚のナイロンに入った紙オシボリを手渡された
彼はもうひとつの方をさっさと食べ始めた
彼女はその湿った紙オシボリでヒザと手のヒラのちょっと血のにじんだ傷口を拭いた
しばらく目の前の食事を見つめていると、彼に食べるように促された
今さら遠慮してもと思い、頂く事にした
彼がまた笑う
何か変な食べ方だったろうか
気になったが、彼の笑願は何故か心地良かった
彼は食べ終わると、会計は済ませてある事を彼女に伝えその場を立ち去ろうとした
一一あ
行ってしまう
無意識に彼の袖をつかむ
彼が振り向いて彼女を見る
恥ずかしくなって慌てて手を隠した
彼はしばらく彼女を見つめると、彼女の手を引きもう片方の手で誰かに電話をし始めた
そしてまた半ば強引に彼女の手と引くと、歩き出した
15分ほど歩いた先はちょっと古めのマンションのドアの前
彼女をそこへ招き入れると、鍵を閉めて出て行ってしまった
数分の間、床に呆然と座っていた
落ち付いてあたりを見わたすと、なかなかの散らかり具合
ちょっとクスッと笑う
(彼女さんとかいないのかな)
(私なんかいて大丈夫かな)
そんな事を考えながら
睡魔が一一一
いつの間にか眠っていた
目が覚めると、見慣れない風景
あ
そうだ
そう、ここは朝出会った男性の部屋
イケナイことをしている気持ちはあったが、
家には帰りたくない
学校さえもどうでも良かった
ただ安心出来る居場所が欲しかった
ずっとここに居て良いか分からなかったが、
先の事を考える余裕は無かった
とりあえずお礼のつもりで部屋の片付け始めた
散らかってはいるが、特に不潔な物はなかった
衣類をたたみ雑誌をまとめー一
ちょっと隅の方へ….
あまり余計な事をしても思い、その後はただ彼の帰りを待つ事にした
急に黙って出て行っても悪いだろう
第一、鍵を持っていない
何をするでもなく、ただ座って一一
あたりが暗くなってきた頃、玄関のドアが開いた
一瞬、驚いたがもちろん彼だった
コンビニの袋を下げて
その袋からお弁当と2つ取り出すと、一つを彼女の方へ
遠慮しつつ、それでも彼女はそれを黙って食べた
彼は何も聞かなかった
ふと部屋が片付いている事に気付き、笑顔で返してくれた
お弁当を食べ終わり、お風呂も借りて
こんなにしてもらっていいのだろうか
心の中で繰り返しながら
お風呂から出ると、彼が部屋着を貸してくれた
かなり大きめだった
何だか照れくさく、でもちょっと幸せな気持ちになった
その日の夜は、彼はソファで彼女はべッドを借りて
申し訳けない気持ちと、これから先の事に考えをめぐらせつつ眠ってしまっていた
ー彼女の決意ー
そんな日が一週間くらい続いた
その間に彼女はある決心をしていた
そしてその夜
彼女は寝ている彼のそばへ
彼女は男性がどうすれば喜ぶかを知っていた
それは彼女が見るのも嫌だったあの光景
だが、今の彼への感謝を伝えるにはそれしかなかった
彼が目を覚ました
怒られるかもと、一瞬身を引いたが彼は彼女を少し見つめた後一
優しく頭をなでて、軽く抱き寄せた
その日二人は初めて一一
繋がった
そうして二人は一つの部屋で一緒に暮らし始めた
一初めての違和感ー
そうして3年も過ぎた頃
彼はいつものように仕事終わりにパチンコ屋へ
最近は二人の関係も慣れてしまって
・・・そう思っていたのは彼だけだったのだが
一緒に暮らし始めた頃は、仕事が終わるとまっすぐ帰宅する事が多かった彼も、次第に帰りが遅くなり
大好きなパチンコへ
もちろん特に帰りたくない事情があった訳ではないけれども
どんなに遅くなっても、何一つ愚痴を言わない彼女に後ろめたい気持ちも感じなくなっていた
ただいつも笑顔で待っていて
そんな生活に慣れてしまっていた
その日は珍しく当たりが続いていた
二千円で初当たりを引くと、確率変動に突入
継続率は80%だが出王の少ない4Rもあり
12Rや16Rも絡めながら10連を超えた
持ち玉は6箱
まだまだ続きそうな気がしていた
時刻は午後21時前
閉店まで時間足りるかな・・なんて事考えながら
いい気分でハンドルを握っていた
……が、そんな時にLINEの着信が鳴る
(なんだよ、こんないい時に)
画面の通知を見ると仕事の関係ではなかったので幾分ほっとした
彼女からだった
付き合ってから今まで帰宅前に彼女からLINEが来る亊はなかった
LINEのやりとりを全くしないワケではなかったが、仕事帰りに連絡があったのは始めてだった
珍しいなと思いながら画面を開くと
【もうちょっと遅くなりそう?】
[?]
[何かあった?]
【ううん】
【気を付けて帰ってきてね】
[分かった]
何か用でもあったかな
‘
まあ急ぐことじゃないんだろ
当たってることだし、終わったてからでいいよな
そう考えながら、また台に向かう
現在15連め
好調!
こんな事は久しぶり
何連するだろうか
20連くらいしたらいいなあ
……
ふと気になる
何の用だったんだろう
今日は早めに帰ってきて欲しかったのかな
……誕生日でもないしな
こんな事今までなかったよな
この連チャンもいつ終わるかまだ分からないし
【ごめん、まだ帰れそうにない】
気になってLINEを入れてみる
ーー5分
ーーーーーー10分
返事がない
もう寝たかなと思いもしたが
いや、先に寝てる事なんて今までなかった
胸がざわざわする
気になってしょうがない
ーーだが当りは続く
(もういいよ)
(止まってくれ)
ーーーまだ当りは続く
(やめようか)
(でも)
(次の当りでやめよう)
ーーーーー当りはさらに続く
(もう次でやめないと)
ようやく終了
「左打ちに戻して下さい」
結局、連チャン途中でヤメきれず24連までさせた
すでに閉店間際
急いで上皿の玉を流し
すぐに店員の呼び出しボタンを押す
なかなか来ない
気が逸(はや)る
玉を流してもらいレシートを受け取る
小走りにカウンタ一に行き景品と交換
交換所で現金を受け取る
その金額につかの間喜びを感じていたが、それ以上に彼女の事が気になった
彼女からの返車は
一まだない
さらに気が焦る
家までは車で15分ほど
車中、何事もない事を祈る
もう嫌な予感しかしない
パチンコなんて途中でやめれば良かった
ー終わりの夜ー
一ーー到着
駐車場から急いで部屋へ
部屋の照明は灯いていた
ドアを開けると
一
一
一
彼女は横たわっていた
すぐさま駆け寄る
(寝てるだけだろ?)
おい
ーーー反応がない
ーーーー心臓が動いていない
おい
おいいいいぃ
ーーーーーもちろん反応はない
涙が出てくる
なんで
なんで
どうすれば
急救車
そうだ、呼ばないと
110? 119?・・・・119!
生まれて初めてかける番号
消防署の職員に状況を伝える
住所?何?
・・・・
ここの住所!
気が動転している
自分でさえ何を言ってるのか分からない
急いで
急いで
頼むから
電話を終えまた彼女を見る
さっきより顔に血の気がないように見える
手をさわると指先が冷たい
ごめん
ごめん
ごめん
ごめん
外でサイレンの音
ドアを開けて消防署の隊員を呼ぶ
状况を聞かれるが、目の前で起きている事以外何も分からない
彼女がタンカに乗せられる
そしてそのまま救急車へ乗せられてゆく
促されて自分も中ヘ
隊員が応救処置に取りかかる
なんとか
なんとかしてくれ
ーーーー都合のいい願いばかりを重ねる自分
分かってる
そんな事は分かっているけどっ
頼む
お願いだからっ
救急病院に着くと彼女はすぐに手術室に運び込まれた
手術室の前に取り残される
ごめん
本当にごめん
ーーー心の中で何度も謝まる
ーーー今さら無駄な行為
頼む
お願いだから
助けて
彼女を
ーーーー自分勝手な願い
ーー繰り返す
深夜1時過ぎ
手術室の扉が開いた
出てきた医師に駆け寄る
「・・・・残念ですが」
ーーーーー
ーーー
ーー
ー
言葉が出ない
ぼうぜんと立ち尽くす
看護師に促され中に入る
彼女が寝ている
いや
一ーー死んで
いる
彼女の前髪をさわる
やわらかい髪
だが肌はすでに冷たく
自分の心の卑しさが恥ずかしく惨めで、彼女を見つめていられなかった
無言で手術室を出ようとすると、側にいた医師に急性心不全と教えらた
その時初めて彼女から開いていた話を思い出した
幼い頃の心臓の手術の話
あの時、思い出していればこうならなかった?
なぜ自分はあの時、パチンコなんか打ってた?
あの時早く帰っていてやれば
彼女は助けを呼んでいたのに
気付いてやれずに
いや
自分が彼女より優先したのだ
パチンコの大当りを
たかがパチンコの・・・
こうして彼はパチンコの大勝ちと引きかえに何よりも大切なものを失った
歩いて帰路につく彼の思考はすでに止まっていた
その道が家へ向かう道なのかも分かっていなかった
その時、
カンカンカンカンカン
警報が鳴るのが聞こえた
赤く激しいランプが交互に点滅する
踏切だった
目の前を遮断機が下りてゆく
彼が遮断器の前で立ち上まる
しばらくして列車が
ーーーー通過
そして、そこにいたはずの
彼の
姿は
消えた
その夜、二人の部屋には誰も戻る事はなかった
次の夜も
ずっと
~終~